こんにちは、ねこ介護士です!私は介護業界の最前線で20年以上、利用者様と向き合ってきた現役の介護福祉士なんです↓↓↓
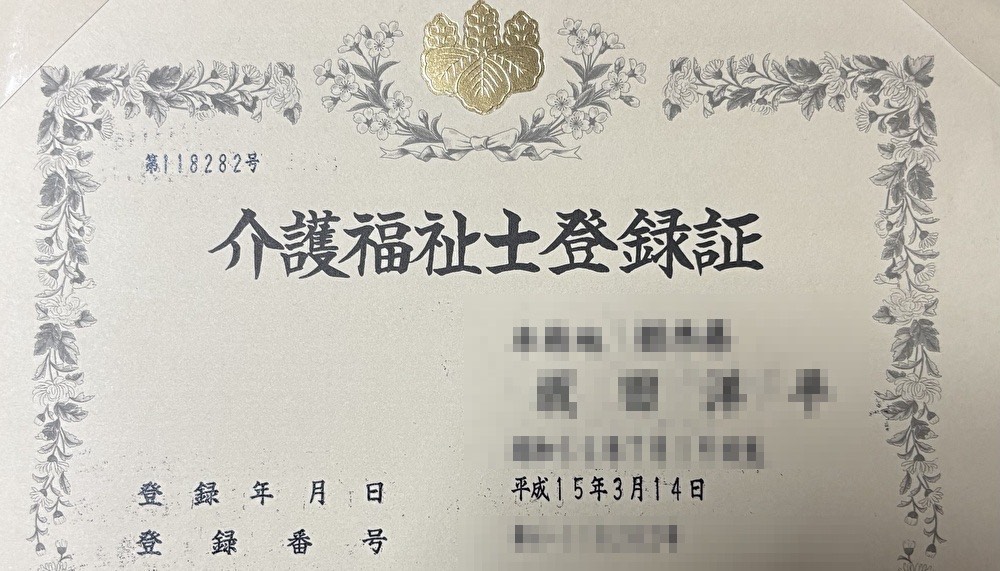
長年の経験で培った知識と視点を活かし、このたび第37回国家試験の過去問題を徹底解説することにしました。
目指したのは、「どの解説サイト、どの解説動画、どの解説本よりも丁寧な解説」です。
単に正解を提示するだけではありません。なぜその選択肢が正解なのか、他の選択肢はなぜ違うのか、そしてその知識が実際の介護現場でどう活かされるのかまで、一問一問じっくりと掘り下げていきます。
では、第37回(令和6年度)介護福祉士国家試験の過去問題【人間の尊厳と自立】を解説します!!!
第37回【人間の尊厳と自立】の過去問題
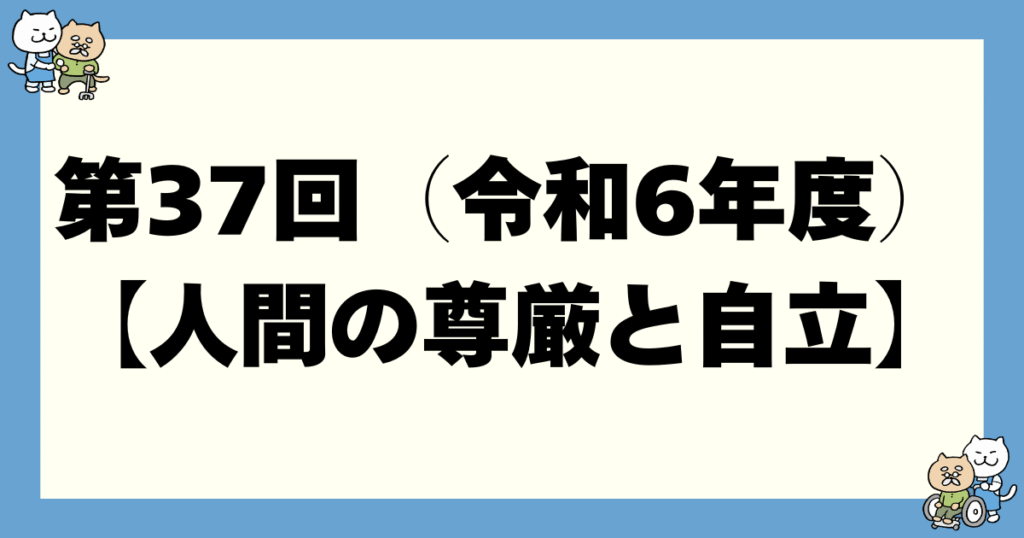
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
アドボカシー(権利擁護)の概念
アドボカシー(Advocacy)とは、利用者の権利や利益を守り、代弁し、擁護する活動のことです。
特に、自分の意思や要望を十分に表現できない利用者に代わって、その人の立場に立って発言・行動することを指します。
アドボカシーの主要な特徴
| 特徴 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 代弁機能 | 利用者に代わって意思を表明する | 認知症の方の「家に帰りたい」という気持ちを家族に伝える |
| 権利擁護 | 利用者の基本的人権を守る | 不適切なケアを受けている利用者を保護する |
| エンパワメント | 利用者の力を引き出し支援する | 自己決定できるよう情報提供や環境整備を行う |
| システム改善 | 制度や環境の改善を働きかける | 施設の規則や地域のサービス改善を提案する |
問題1の各項目の解説
選択肢1:介護を行う前には,利用者に十分な説明をして同意を得る
×不正解
これはインフォームドコンセントの概念です。利用者の自己決定権を尊重する重要な行為ですが、アドボカシーとは異なります。インフォームドコンセントは利用者自身が判断・決定できる状況での対応であり、代弁や擁護の要素は含まれていません。
選択肢2:利用者の介護計画を作成するときに,他職種に専門的な助言を求める
×不正解
これはチームアプローチや多職種連携の概念です。より良いケアを提供するための専門的な協働ですが、利用者の権利擁護や代弁という直接的な要素は含まれていません。
選択肢3:利用者個人の趣味を生かして,レクリエーション活動を行う
×不正解
これは個別ケアやパーソン・センタード・ケアの概念です。利用者の個性や嗜好を尊重する重要な取り組みですが、権利擁護や代弁の機能は含まれていません。
選択肢4:希望を言い出しにくい利用者の意思をくみ取り,その実現に向けて働きかける
○正解
これこそがアドボカシーの本質です。利用者が自分で意思表示することが困難な状況において、介護福祉職が:
- 利用者の立場に立って考える(当事者の視点)
- 言葉にできない思いや希望を察知する(意思のくみ取り)
- その実現に向けて具体的な行動を取る(代弁・擁護活動)
という一連のプロセスを含んでいます。
選択肢5:視覚障害者が必要とする情報を,利用しやすいようにする
×不正解
これは合理的配慮やアクセシビリティの向上の概念です。障害者の権利を保障する重要な取り組みですが、代弁や擁護という能動的な働きかけではなく、環境整備の側面が強い対応です。
アドボカシーの具体的な実践例
事例1:認知症高齢者の場合
状況:認知症のAさんが「家に帰りたい」と繰り返し訴えるが、家族は「施設にいた方が安全」と考えている。
アドボカシー実践:
- Aさんの「帰りたい」という気持ちの背景を探る
- 家族に対してAさんの心境を代弁する
- 一時帰宅や面会頻度の増加など妥協案を提案する
- Aさんの尊厳と安全の両立を図る
事例2:身体障害者への場合
状況:車椅子利用者のBさんが地域イベントに参加したいが、バリアが多く諦めかけている。
アドボカシー実践:
- Bさんの参加意欲を受け止め、権利として支援する
- 主催者に対してアクセシビリティの改善を働きかける
- 必要な支援体制の構築を提案・調整する
- Bさんの社会参加の権利を擁護する
ここからが【人間の尊厳と自立】の第2問目になります!
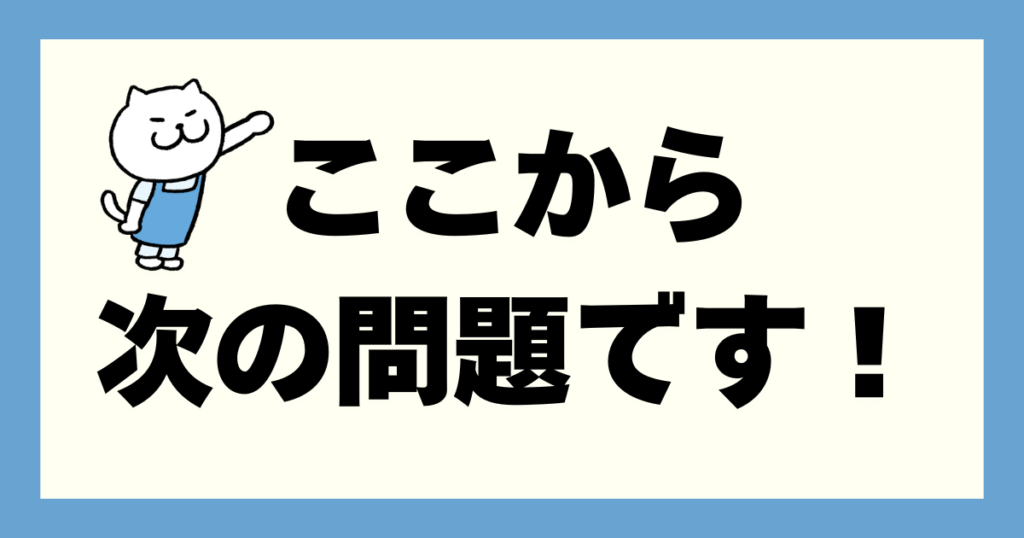
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
5番:「Aさんが依頼する理由を,まず考えてみることが大切です」
問題の背景分析
この問題は実習指導における重要な考え方を問うものです。利用者の行動変化に対して、実習生がどのような思考プロセスを身につけるべきかを示しています。
重要なポイント
- Aさんは従来車いすを自走していた
- 実習生が来てから行動が変化した
- 「腕が痛い」という理由で介助を求めるようになった
- この変化には必ず理由がある
考えられる理由の分析
| 考えられる理由 | 背景 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 身体的な変化 | 実際に腕に痛みや不調がある | 医療職への相談、評価の実施 |
| 心理的な要因 | 実習生との関わりを求めている | コミュニケーションの機会を設ける |
| 環境の変化 | 新しい人が来たことへの反応 | 安心できる関係性の構築 |
| 注目欲求 | 実習生の関心を引きたい | 適切な関わり方の検討 |
問題2の各項目の解説
| 選択肢 | 問題点 | 理由 |
|---|---|---|
| 1番 「Aさんの腕は痛くないので,気にしないでください」 | 根拠のない判断 | 実際の痛みの有無を確認せずに決めつけている |
| 2番 「どのようなときも,Aさん自身で行ってもらうことが必要です」 | 画一的な対応 | 個別性を無視した一律的な判断 |
| 3番 「ご家族から自分で行うように,言われています」 | 責任の転嫁 | 家族の意向を理由にして思考を停止している |
| 4番 「それは自立につながらないので,車いすを押さないでください」 | 短絡的な判断 | 理由を考えずに結論を出している |
| 5番 「Aさんが依頼する理由を,まず考えてみることが大切です」 | 最も適切 | 問題解決の基本的な思考プロセスを示している |
第2問目のまとめ
この問題は、介護実践において最も重要な「利用者理解」の基本的な姿勢を問うものです。表面的な現象に対して即座に判断するのではなく、「なぜそうなったのか」を考える思考プロセスこそが、質の高い介護実践につながります。
実習指導者は、実習生に対して答えを与えるのではなく、考える力を育成することが最も重要な役割です。選択肢5番は、この教育的な観点を最もよく表している適切な助言といえます。
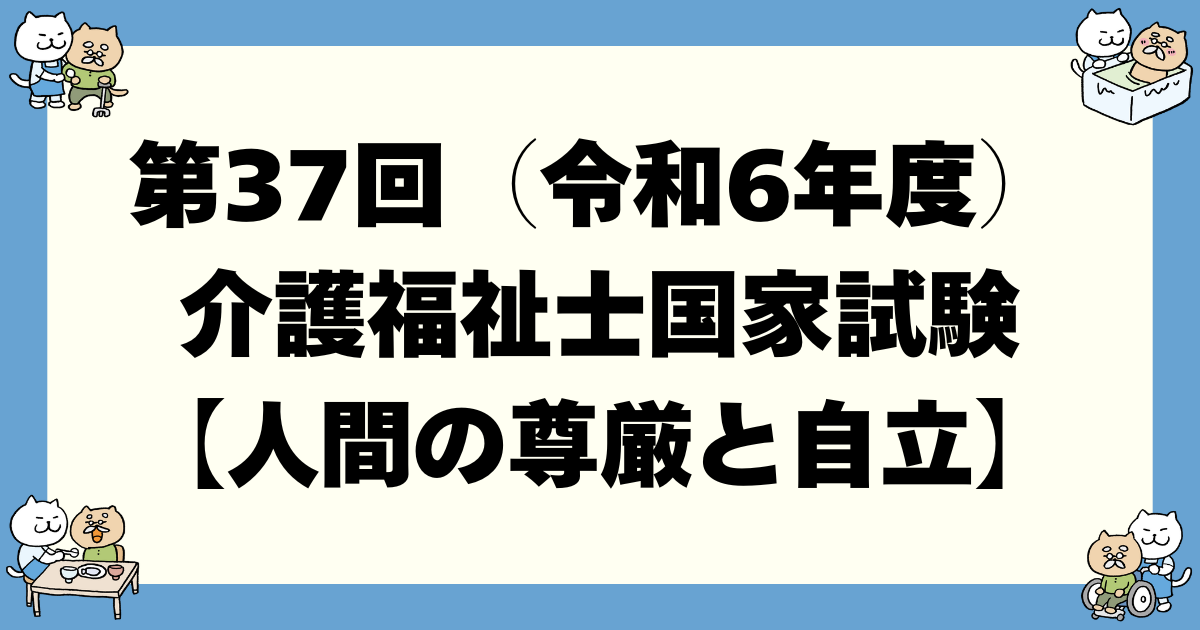
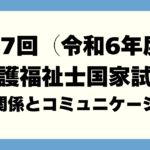
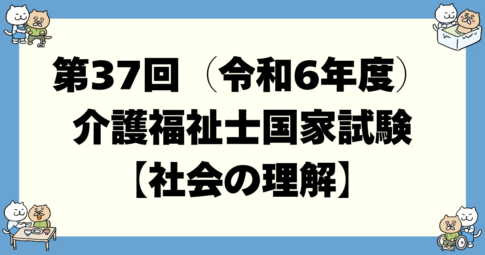
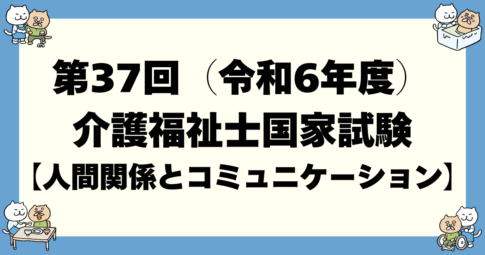
4番:希望を言い出しにくい利用者の意思をくみ取り,その実現に向けて働きかける。