こんにちは、ねこ介護士です!私は介護で20年以上、利用者さんと歩んできた現役の介護福祉士です。
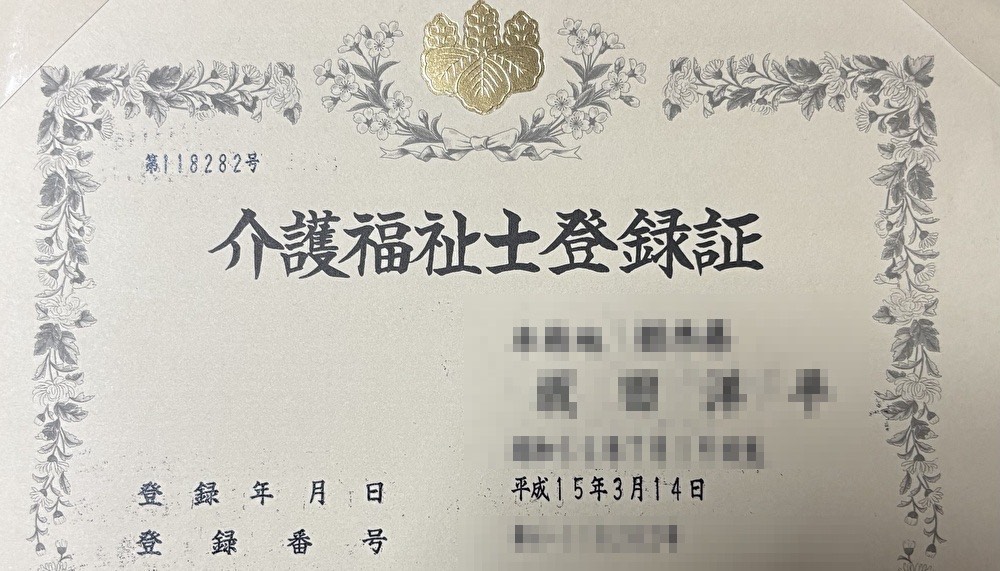
長年の経験をすべて注ぎ込み、どこよりも分かりやすい解説を作りました。
- なぜ、これが正解なの?
- 他の選択肢は、どこが違うの?
- この知識、現場でどう役立つの?
あなたの「?」が「!」に変わるまで、じっくり丁寧に解説します。
では早速、第37回(令和6年度)介護福祉士国家試験【社会の理解】の解説をします!
第37回【社会の理解】の過去問題
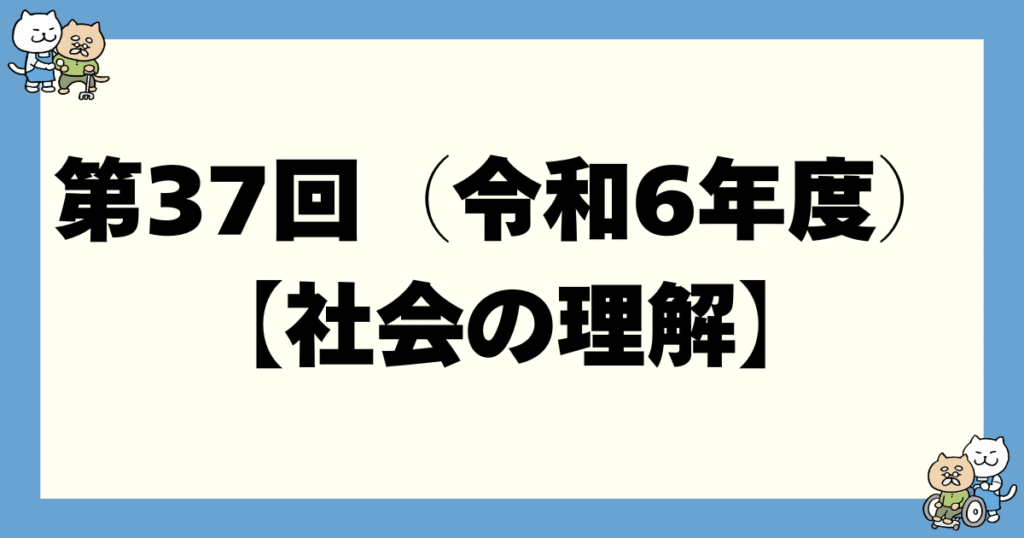
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
問題7の各項目の解説
選択肢1:収益事業は禁止されている。【不適切】
社会福祉法人は、社会福祉事業及び公益事業のほか、収益事業を行うことができます。ただし、収益事業から生じた収益は社会福祉事業又は公益事業に充てなければなりません。
根拠:社会福祉法第26条第1項・第3項
選択肢2:所轄庁は内閣府である。【不適切】
社会福祉法人の所轄庁は内閣府ではありません。原則として都道府県知事が所轄庁となり、指定都市・中核市においてはその市長が所轄庁となります。事業の種類や規模により所轄庁が決まります。
根拠:社会福祉法第30条
選択肢3:設立時に所轄庁の認可は不要である。【不適切】
社会福祉法人の設立には、所轄庁の認可が必要です。設立の認可を受けることによって法人格を取得し、登記によって成立します。認可制により、適格性と継続性が担保されています。
根拠:社会福祉法第25条
選択肢4:評議員会を置く必要がある。【適切】
平成28年の社会福祉法改正により、すべての社会福祉法人は評議員会を置くことが義務付けられました。評議員会は法人の最高意思決定機関として位置づけられ、理事の選任・解任、重要事項の決議等を行います。この改正により、ガバナンスの強化が図られました。
根拠:社会福祉法第40条(平成28年改正、平成29年4月1日施行)
選択肢5:解散は禁止されている。【不適切】
社会福祉法人は以下の事由により解散することができます:①評議員会の決議、②定款で定めた解散事由の発生、③目的たる事業の成功の不能、④破産手続開始の決定、⑤所轄庁による解散命令。解散は禁止されていません。
根拠:社会福祉法第46条
第7問目のまとめ
社会福祉法人制度は、平成28年の社会福祉法改正により大きく変わりました。特に評議員会の設置義務化は、従来の理事会中心の運営から、より民主的で透明性の高いガバナンス体制への転換を意味します。
この改正により、社会福祉法人の経営の透明性向上と適正化が図られ、国民の信頼確保につながることが期待されています。
受験においては、この平成28年改正の内容、特に評議員会に関する規定は頻出事項として押さえておく必要があります。
ここからが【社会の理解】の第8問目になります!
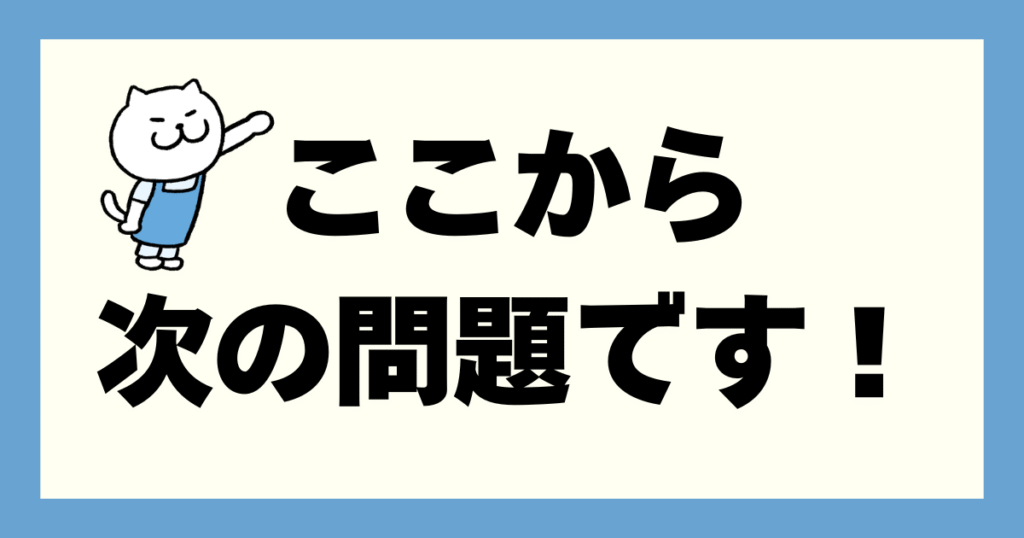
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
2番:日中・夜間を通じて,提供するサービスである。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス内容 | 定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス、訪問看護サービス |
| 提供時間 | 24時間365日(日中・夜間を通じて) |
| 対象者 | 要介護1~5の認定を受けた者 |
| 指定・監督機関 | 市町村(地域密着型サービス) |
| 利用定員 | 特に定めなし(訪問型サービスのため) |
| サービス提供場所 | 利用者の居宅 |
問題8の各項目の解説
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1. 利用定員は,9人以下と定められている。 | × | 訪問型サービスのため、利用定員の設定はありません。9人以下の定員が設定されるのは小規模多機能型居宅介護などです。 |
| 2. 日中・夜間を通じて,提供するサービスである。 | ○ | 24時間365日体制でサービスを提供する点が最大の特徴です。定期巡回、随時対応・訪問を組み合わせて実施します。 |
| 3. 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)に入居する利用者に対して,機能訓練を行うサービスである。 | × | これは居住系サービス内での機能訓練の説明です。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は在宅の利用者に提供するサービスです。 |
| 4. 通い,泊まり,看護の3種類の組合せによるサービスである。 | × | これは小規模多機能型居宅介護の説明です。正しくは「通い、泊まり、訪問」の組み合わせです。 |
| 5. 都道府県が事業者の指定,指導,監督を行うサービスである。 | × | 地域密着型サービスのため、市町村が指定・指導・監督を行います。都道府県ではありません。 |
サービスの特徴
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、平成24年度に創設された地域密着型サービスです。
重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時対応を行います。
ここからが【社会の理解】の第9問目になります!
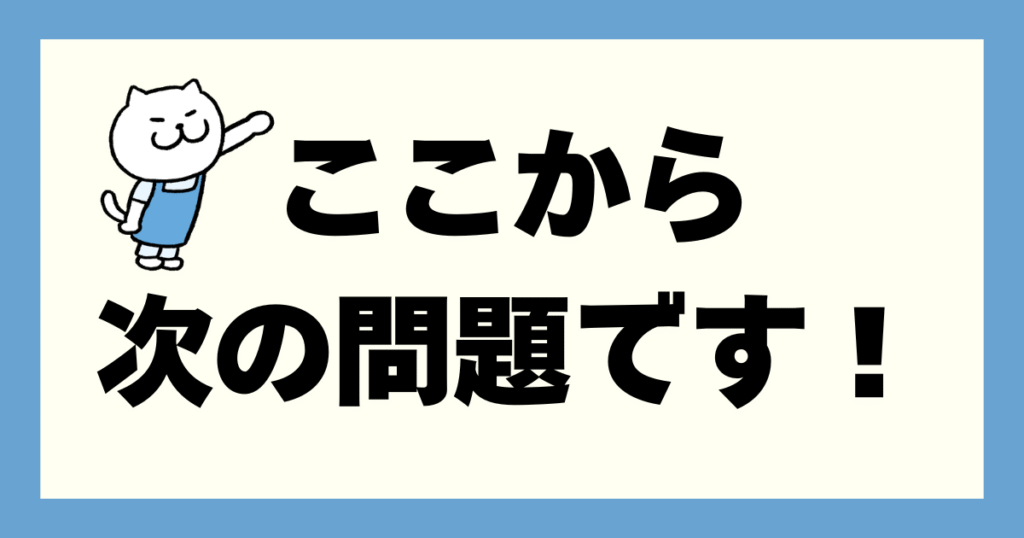
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解:5 生存権
生存権とは?
生存権の憲法的根拠
この事例で最も重要な権利は「生存権」です。生存権は日本国憲法第25条に規定されており、すべての国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障しています。
日本国憲法第25条
第1項:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項:国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
事例における生存権の適用
Aさんの状況を分析すると、以下の点で生存権が直接的に関わっています:
1.うつ症状による退職後、経済的困窮に陥った状況
2.頼れる親族がなく、自力での生活維持が困難になった状態
3.生活保護制度を利用することで、憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を確保
生活保護制度は、まさに憲法第25条の生存権を具体化した社会保障制度であり、Aさんがこの制度を受給する権利は憲法によって保障されています。
問題8の各項目の解説
| 選択肢 | 権利の内容 | 憲法条文 | 事例との関連性 | 適切性 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 団体交渉権 | 労働者が使用者と対等な立場で交渉する権利 | 第28条 | Aさんは既に退職しており、労働関係にない | × |
| 2. 平等権 | 法の下の平等を保障する権利 | 第14条 | 差別的取扱いの問題は事例に含まれていない | × |
| 3. 財産権 | 私有財産を保障する権利 | 第29条 | 財産の侵害ではなく、経済的困窮の問題 | × |
| 4. 思想の自由 | 内心の自由を保障する権利 | 第19条 | 思想・信条に関する問題ではない | × |
| 5. 生存権 | 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利 | 第25条 | 生活保護受給により直接的に保障される権利 | ◎ |
第8問目のまとめ
正解:5 生存権
Aさんが生活保護を受給する権利は、日本国憲法第25条に規定された生存権に基づいています。
この権利は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むことを保障するものであり、生活保護制度はその具体的な実現手段として機能しています。
事例では、Aさんがうつ症状による退職後に経済的困窮に陥り、頼れる親族もない状況で生活保護を受給することになりましたが、これは憲法が保障する基本的人権の行使にほかなりません。
他の選択肢(団体交渉権、平等権、財産権、思想の自由)は、いずれもこの事例の核心的な問題である「生活困窮からの脱却と最低限度の生活の保障」とは直接的な関連性がないため、適切ではありません
ここからが【社会の理解】の第10問目になります!
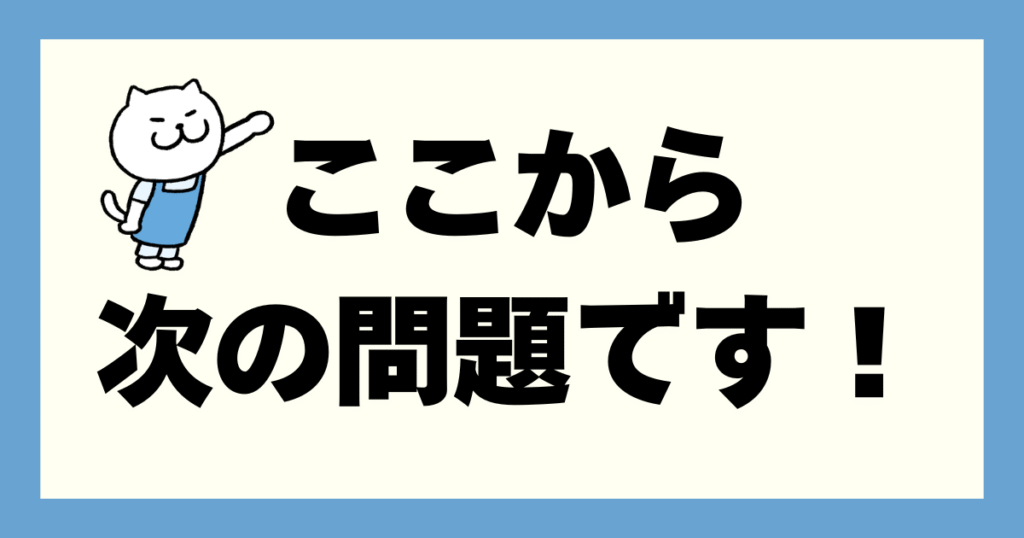
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
3番:業務には精神保健に関する事項が含まれている。
保健所は地域保健法に基づいて設置される地域保健の拠点となる行政機関です。都道府県、指定都市、中核市、その他政令で定める市が設置主体となります。保健所の業務は多岐にわたり、地域住民の健康保持・増進を図る重要な役割を担っています。
問題10の各選択肢の解説
| 選択肢 | 内容 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保健師助産師看護師法に基づいて設置されている | × | 地域保健法に基づいて設置される。保健師助産師看護師法は職種の資格に関する法律である。 |
| 2 | すべての市町村に設置の義務がある | × | 都道府県、指定都市、中核市等が設置する。すべての市町村に設置義務はない。 |
| 3 | 業務には精神保健に関する事項が含まれている | ○ | 地域保健法第6条により、精神保健に関する事項は保健所の業務として明記されている。 |
| 4 | 歯科衛生士を置かなくてはならない | × | 必置職員は医師、薬剤師、獣医師、保健師など。歯科衛生士は必置ではない。 |
| 5 | 児童の一時保護を行う | × | 児童の一時保護は児童相談所の業務である。保健所の業務ではない。 |
第10問目のまとめ
正解は3番「業務には精神保健に関する事項が含まれている」
重要ポイント
- 保健所は地域保健法に基づいて設置される地域保健の拠点機関である
- 精神保健業務は保健所の法定業務の一つとして明確に位置づけられている
- 設置主体は都道府県、指定都市、中核市等であり、すべての市町村ではない
- 児童の一時保護は児童相談所の業務であり、保健所の業務ではない
- 必置職員に歯科衛生士は含まれていない
保健所は地域住民の健康を守る重要な行政機関として、感染症対策、食品衛生、環境衛生、精神保健など幅広い分野で活動しています。
特に精神保健分野では、相談業務や社会復帰支援など、地域の精神保健の向上に重要な役割を果たしています。
ここからが【社会の理解】の第11問目になります!
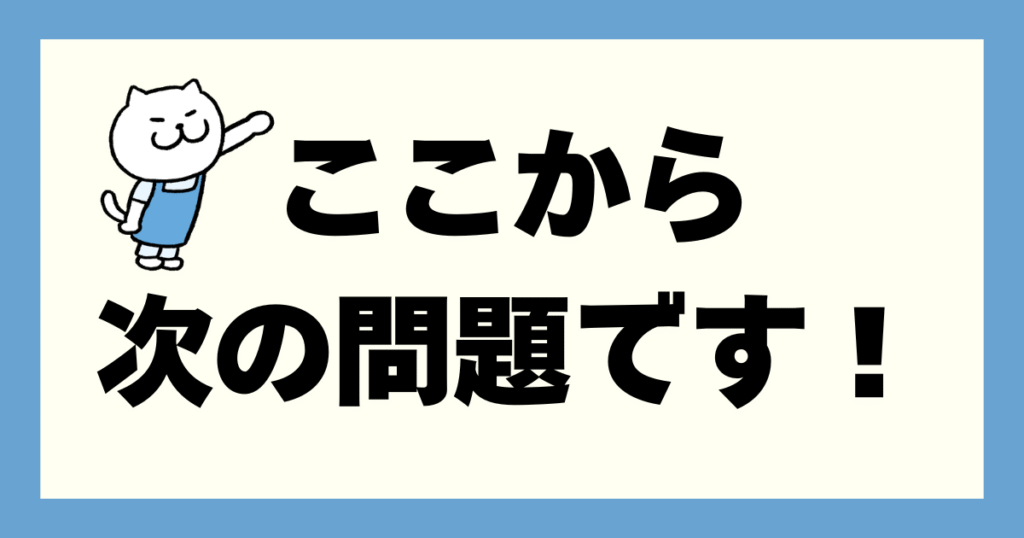
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解:1番「地域ケア会議の開催」
地域包括支援センターの業務について
地域包括支援センターは、介護保険法に基づいて設置される機関で、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、包括的な支援を行う拠点です。
主な業務内容
- 包括的支援事業
- 介護予防ケアマネジメント業務
- 総合相談支援業務
- 権利擁護業務
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
- 地域ケア会議の開催
- 介護予防支援業務
- 認知症施策の推進
- 生活支援体制整備事業
問題11の各選択肢の解説
| 選択肢 | 内容 | 正誤 | 詳細解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | 地域ケア会議の開催 | 正しい | 地域包括支援センターの主要業務の一つです。個別ケースの検討から地域課題の発見・解決まで、多職種協働による会議を開催し、地域包括ケアシステムの構築を推進します。 |
| 2 | 施設サービスのケアプランの作成 | 間違い | 施設サービス(特養、老健等)のケアプランは、各施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成します。地域包括支援センターは居宅サービスの介護予防支援を行います。 |
| 3 | 成年後見制度の申請 | 間違い | 地域包括支援センターは成年後見制度の相談・情報提供・申立支援は行いますが、申請自体は家庭裁判所に対して本人や家族等が行います。センターは権利擁護業務として支援を提供します。 |
| 4 | 介護認定審査会の設置 | 間違い | 介護認定審査会は市町村(保険者)が設置・運営します。地域包括支援センターは市町村から委託を受けて運営される機関であり、審査会の設置権限はありません。 |
| 5 | 地域密着型サービスの事業者の指導・監督 | 間違い | 地域密着型サービス事業者の指定・指導・監督は市町村が行います。地域包括支援センターは事業者との連携や調整は行いますが、指導・監督権限はありません。 |
第11問目のまとめ
正解:1番「地域ケア会議の開催」
重要ポイント
- 地域包括支援センターは地域包括ケアシステムの中核的機関
- 地域ケア会議は法定業務として位置づけられている
- 施設ケアプラン作成は施設の介護支援専門員の業務
- 成年後見制度申請は家庭裁判所への申立て(センターは支援)
- 介護認定審査会設置は市町村の権限
- 事業者指導監督は市町村の権限
地域包括支援センターの業務を理解する際は、「地域包括ケアシステムの構築」という目的を念頭に置き、他機関との役割分担を整理することが重要です。
ここからが【社会の理解】の第12問目になります!
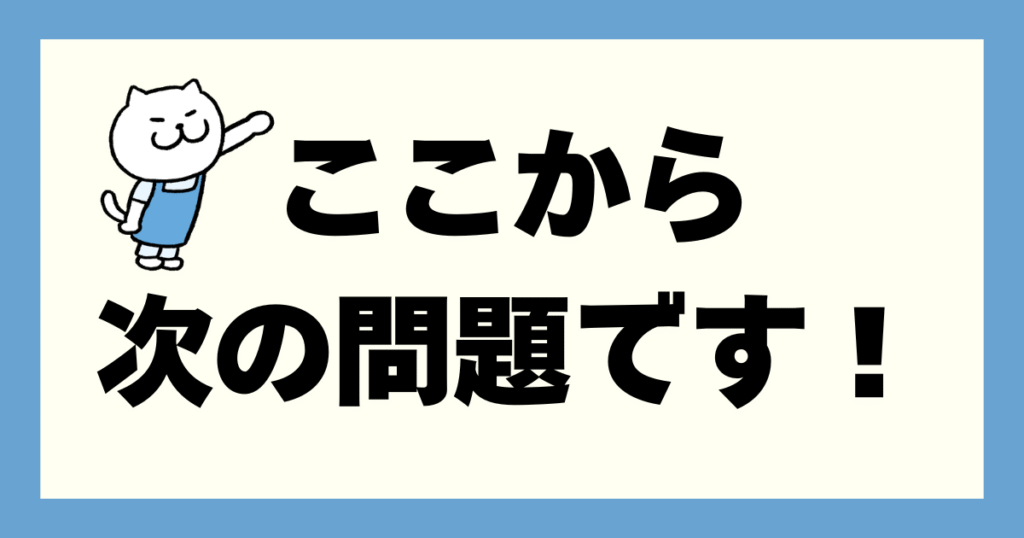
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解:3 第一号通所事業(通所型サービス)
Bさんの状況分析
基本情報
- 年齢・性別:85歳男性
- 要介護度:要支援1(軽度の支援が必要な状態)
- 居住状況:自宅で一人暮らし
- 身体状況:最近物忘れが多くなっている
- 現在利用中のサービス:地域支援事業の訪問型サービス
ニーズ
- 希望:これからも自宅で生活したい(在宅継続の意志)
- 課題:日中の話し相手がいなくて寂しい(社会的孤立感)
問題12の各選択肢の解説
| 選択肢 | サービス名 | サービス内容・特徴 | Bさんのケースとの適合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症高齢者が共同生活を行う住居型施設。24時間体制でケアを提供。要支援2以上が対象。 | 不適切 ・要支援1は利用不可 ・施設入所により在宅生活継続の希望に合わない |
| 2 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 常時介護が必要で在宅生活が困難な高齢者の生活施設。原則要介護3以上が対象。 | 不適切 ・要支援1は利用不可 ・施設入所により在宅生活継続の希望に合わない |
| 3 | 第一号通所事業(通所型サービス) | 要支援者を対象とした日中の通所サービス。機能訓練、レクリエーション、入浴、食事などを提供。他の利用者との交流機会もある。 | 最適 ・要支援1で利用可能 ・在宅生活を継続できる ・日中の話し相手・交流の場を提供 ・孤立感の解消が期待できる |
| 4 | 夜間対応型訪問介護 | 夜間帯(18時~8時)に定期巡回や随時対応を行う訪問サービス。緊急時対応も含む。 | 不適切 ・日中の孤立感という課題に対応していない ・Bさんの現在のニーズとは時間帯が合わない |
| 5 | 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理・指導を行うサービス。 | 不適切 ・医療的な管理・指導が主目的 ・社会的孤立感や話し相手のニーズには対応していない |
正解が最も適切な理由
第一号通所事業(通所型サービス)が最適な理由
1. 制度上の適合性
- 要支援1のBさんが利用できるサービスである
- 地域支援事業の総合事業に含まれ、既に訪問型サービスを利用しているBさんにとって連続性がある
2. ニーズへの直接的対応
- 「日中の話し相手がいない」という課題に対し、他の利用者やスタッフとの交流機会を提供
- 「これからも自宅で生活したい」という希望を尊重し、在宅生活の継続を支援
3. 包括的な効果
- 社会的孤立感の解消
- 身体機能・認知機能の維持・向上
- 生活リズムの確立
- 家族(いる場合)の介護負担軽減
第12問目のまとめ
Bさんのケースでは、要支援1という軽度の要介護状態で、在宅生活継続の強い意志を持ちながらも、日中の社会的孤立感という明確な課題を抱えています。
第一号通所事業(通所型サービス)は、これらすべての要素に対応できる最も適切なサービスです。
制度上の利用要件を満たし、Bさんの希望する在宅生活を継続しながら、日中の交流の場を提供することで孤立感を解消し、さらに身体機能・認知機能の維持向上も期待できます。
他の選択肢は、要介護度の要件を満たさない(選択肢1、2)、ニーズとの時間的不一致(選択肢4)、目的の相違(選択肢5)などの理由で不適切です。
このように、利用者の要介護度、生活継続への意向、具体的なニーズを総合的に判断してサービスを選択することが、適切な介護支援につながります。
ここからが【社会の理解】の第13問目になります!
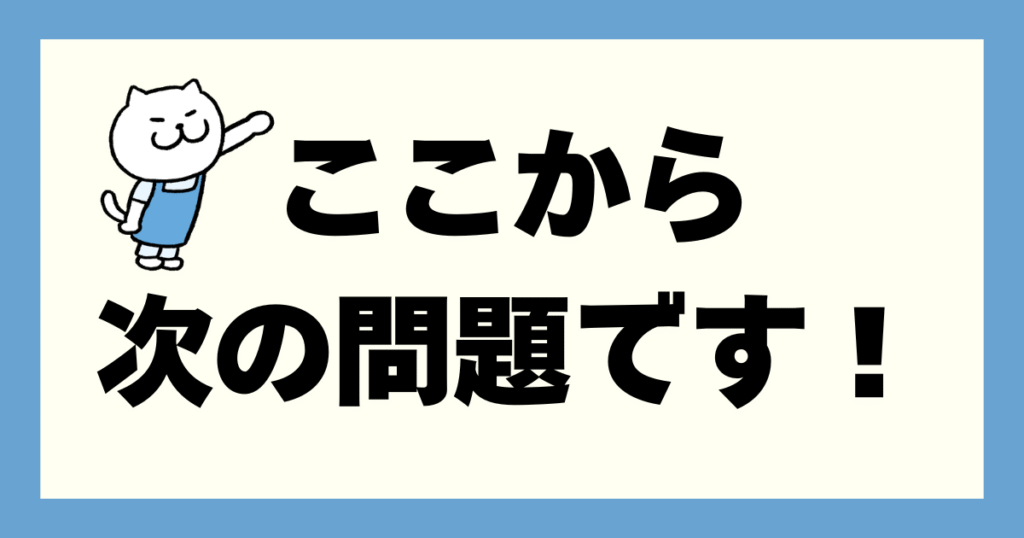
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解:4 財源には,第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる。
問題13の各選択肢の詳しい解説
選択肢1:第1号被保険者の保険料は,都道府県が徴収する。
【不正解】第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、市町村(保険者)が徴収します。都道府県ではありません。
選択肢2:第1号被保険者の保険料は,全国一律である。
【不正解】第1号被保険者の保険料は市町村ごとに異なります。各市町村の介護サービス費用や高齢化率などに応じて設定されるため、全国一律ではありません。
選択肢3:第2号被保険者の保険料は,年金保険の保険料と合わせて徴収される。
【不正解】第2号被保険者(40~64歳)の介護保険料は、医療保険の保険料と合わせて徴収されます。年金保険ではありません。
選択肢4:財源には,第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる。
【正解】介護保険の財源は、第1号被保険者の保険料、第2号被保険者の保険料、および公費(国・都道府県・市町村)で構成されています。
選択肢5:介護保険サービスの利用者負担割合は,一律,1割である。
【不正解】利用者負担割合は所得に応じて1割、2割、3割に区分されており、一律1割ではありません。
介護保険制度の財源構造
| 財源の種類 | 負担割合 | 詳細 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者保険料 | 23% | 65歳以上の被保険者 |
| 第2号被保険者保険料 | 27% | 40~64歳の被保険者 |
| 国庫負担 | 25% | 施設等給付費は20% |
| 都道府県負担 | 12.5% | 施設等給付費は17.5% |
| 市町村負担 | 12.5% | 保険者としての負担 |
被保険者の分類と保険料徴収方法
| 被保険者 | 年齢 | 保険料徴収方法 | 徴収主体 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 年金からの特別徴収または普通徴収 | 市町村 |
| 第2号被保険者 | 40~64歳 | 医療保険料と合わせて徴収 | 各医療保険者 |
第13問目のまとめ
介護保険制度の重要なポイント:
- 保険者:市町村(特別区を含む)
- 財源構成:被保険者の保険料50%、公費50%
- 第1号被保険者:65歳以上、市町村が保険料徴収、市町村ごとに保険料額が異なる
- 第2号被保険者:40~64歳、医療保険料と合わせて徴収
- 利用者負担:所得に応じて1~3割の負担
正解の選択肢4は、介護保険制度の基本的な財源構造を正しく述べており、第1号・第2号被保険者の保険料が財源に含まれることを示しています。
ここからが【社会の理解】の第14問目になります!
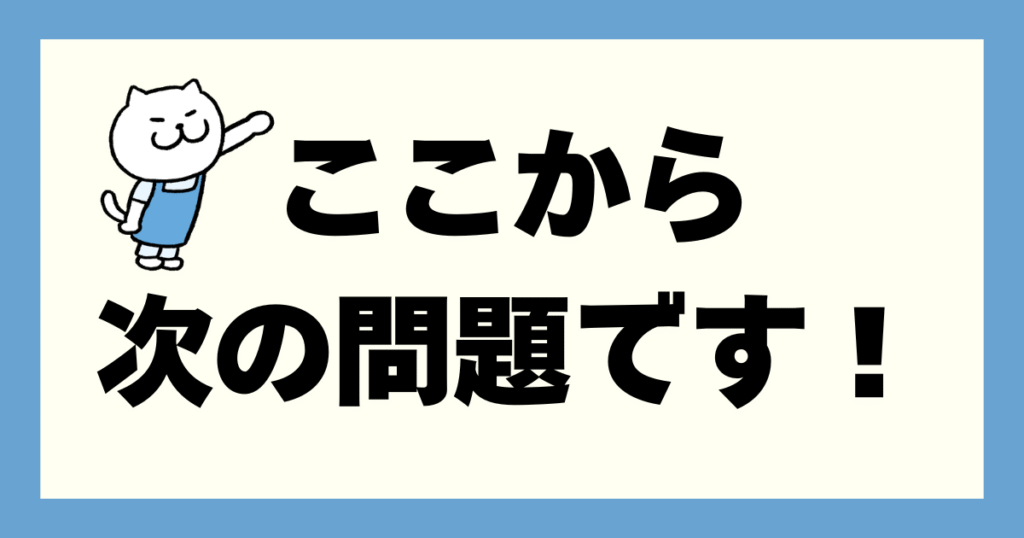
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解:1 2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は,2.5%である。
問題14の各選択肢の解説
選択肢1:2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は,2.5%である。【正解】
2024年4月1日より、民間企業の障害者法定雇用率は2.3%から2.5%に引き上げられました。これは段階的な引き上げの一環で、さらに2026年7月には2.7%まで引き上げられる予定です。
選択肢2:精神障害者は,法定雇用率の対象から除外されている。【誤り】
2018年4月1日から精神障害者も法定雇用率の算定基礎に加えられており、現在は身体障害者、知的障害者とともに法定雇用率の対象となっています。
選択肢3:2024年度(令和6年度)に,障害者の雇用義務が生じるのは,従業員101人以上の事業主である。【誤り】
2024年度も従来通り、常時雇用労働者数が43.5人以上(2.3%時代は43.5人、2.5%では40人以上)の事業主に障害者雇用義務があります。101人という数字は不正確です。
選択肢4:週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。【誤り】
2023年4月から、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者について、雇用率の算定において0.5カウントとして取り扱うことが可能になりました。
選択肢5:2024年度(令和6年度)の事業主支援(助成金)は,2023年度(令和5年度)以前と同じである。【誤り】
障害者雇用に関する助成金制度は毎年見直しが行われており、2024年度には支給要件や支給額等の変更があります。
2024年度の障害者雇用制度の主な変更点
| 項目 | 変更前(2023年度まで) | 変更後(2024年度から) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2026年7月には2.7%予定 |
| 国・地方公共団体 | 2.6% | 2.8% | 2026年7月には3.0%予定 |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.5% | 2.7% | 2026年7月には2.9%予定 |
| 雇用義務が発生する企業規模 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 法定雇用率引き上げにより |
重要ポイント:短時間労働(週10-20時間)の精神障害者等の雇用率算定が2023年4月から可能になり、より柔軟な働き方が促進されています。
第14問目のまとめ
2024年度の障害者雇用促進法の最も重要な変更点は、民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられたことです。
これにより、障害者雇用義務が発生する企業の規模も従業員40人以上に拡大されました。
また、近年の制度改正により以下の点も重要です。
- 精神障害者が法定雇用率の算定対象に含まれること(2018年4月〜)
- 週10-20時間の短時間労働者も雇用率算定の対象となること(2023年4月〜)
- 助成金制度が毎年見直されていること
これらの制度変更は、障害者の多様な働き方を支援し、より多くの企業での障害者雇用を促進することを目的としています。
ここからが【社会の理解】の第15問目になります!
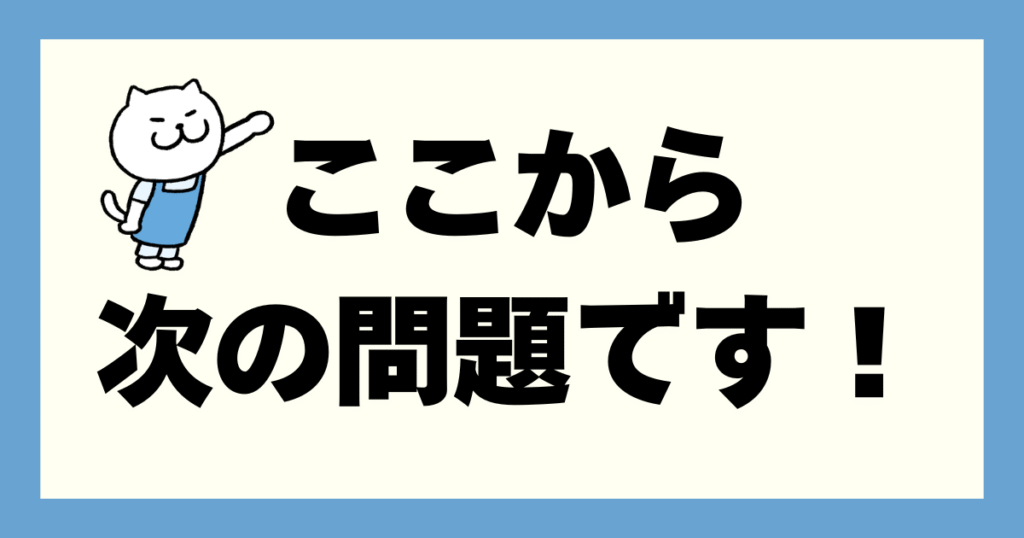
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解:2 短期入所は介護給付の1つである。
問題15の各選択肢の解説
選択肢1:介護給付費の支給を受けるときに,障害支援区分の認定は不要である。
【不適切】
介護給付費の支給を受けるためには、原則として障害支援区分の認定が必要です。障害支援区分は、障害者の心身の状況を総合的に示すものとして区分1から区分6までの6段階で認定され、介護の必要度を判定する重要な基準となります。
選択肢2:短期入所は介護給付の1つである。
【適切】
短期入所(ショートステイ)は介護給付に含まれるサービスです。居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所が必要な場合に利用できる重要なサービスです。
選択肢3:地域生活支援事業は,国が実施主体である。
【不適切】
地域生活支援事業の実施主体は市町村(一部は都道府県)です。国は予算の一部を補助しますが、実際の事業運営は地方自治体が行います。地域の特性に応じた柔軟なサービス提供が特徴です。
選択肢4:自立支援給付は応益負担である。
【不適切】
障害者総合支援法では、利用者負担は応益負担ではなく「応能負担」が原則です。利用者とその配偶者の所得に応じて負担上限月額が設定され、所得の低い方には軽減措置が適用されます。
選択肢5:行動援護は訓練等給付の1つである。
【不適切】
行動援護は介護給付に分類されるサービスです。知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有する方に対して、行動する際の危険を回避するために必要な支援を行うサービスです。
第15問目のまとめ
障害者総合支援法のサービス体系を理解する上で重要なポイントは以下の通りです:
- 介護給付:日常生活に介護が必要な方への支援で、短期入所も含まれる
- 訓練等給付:自立や就労を目指すための訓練・支援サービス
- 障害支援区分:介護給付を利用する際に必要な認定制度
- 応能負担:所得に応じた負担で、低所得者には配慮がある
- 地域生活支援事業:市町村が実施主体となる地域密着型サービス
本問題では、短期入所が介護給付の一つであることが正解であり、障害者の地域生活を支える重要なレスパイトサービスとして位置づけられています。
ここからが【社会の理解】の第16問目になります!
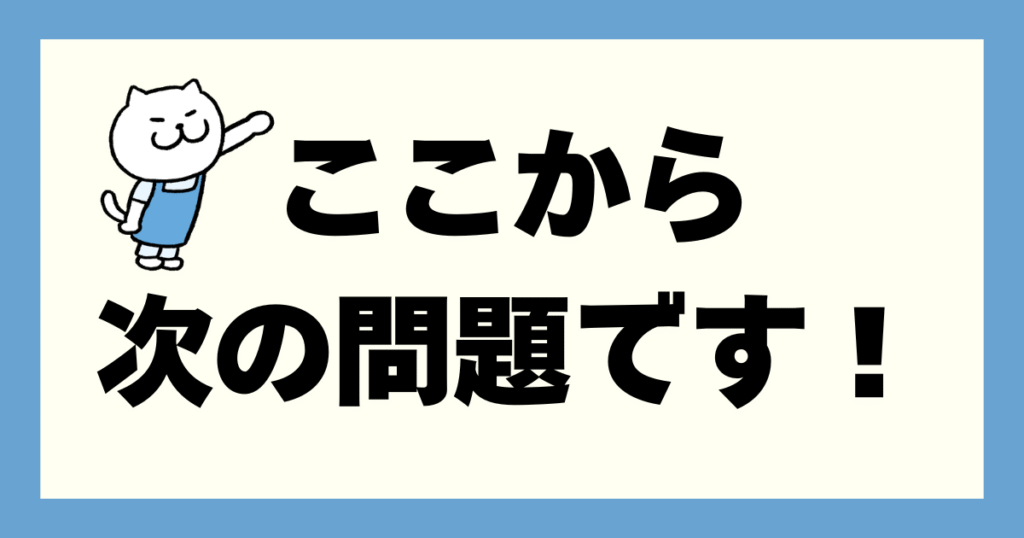
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解:5番 保育所等訪問支援は,保育所等を訪問し,障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う。
問題16の各選択肢の解説
| 選択肢 | 正誤 | 説明 |
|---|---|---|
| 1番 | × | 障害児支援サービスの利用に療育手帳は必須ではない。障害児通所給付費の支給決定は、医師の意見書や発達検査結果等により判断され、手帳の有無は要件ではない。 |
| 2番 | × | 放課後等デイサービスは「児童福祉法」に基づく障害児通所支援サービスである。子ども・子育て支援法ではなく、障害児支援制度として位置づけられている。 |
| 3番 | × | 障害児通所支援を利用する際は、障害児支援利用計画の作成が必要である。これは障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作成し、適切な支援の提供を確保するための重要な書類である。 |
| 4番 | × | 障害児入所支援の実施主体は都道府県・指定都市である。市町村ではなく、より広域的な自治体が責任を持って実施する制度となっている。 |
| 5番 | ○ | 保育所等訪問支援の説明として適切である。障害児が通う保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を提供するサービスである。 |
保育所等訪問支援とは?
保育所等訪問支援は、障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することを目的としています。
対象施設
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 小学校
- 特別支援学校
- その他児童が集団生活を営む施設
支援内容
- 障害児本人に対する支援(集団生活への適応のための訓練等)
- 訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導等)
第16問目のまとめ
障害児支援制度は児童福祉法に基づき、障害のある児童とその家族を支援する重要な制度です。主なポイントは以下の通りです:
- 利用要件:療育手帳は必須ではなく、医師の意見書や発達検査等により判断される
- 法的根拠:児童福祉法が基本となる法律(子ども・子育て支援法ではない)
- 計画作成:障害児支援利用計画の作成が必要
- 実施主体:通所支援は市町村、入所支援は都道府県・指定都市
- 保育所等訪問支援:集団生活への適応を支援する重要なサービス
これらの制度を正しく理解し、障害児とその家族のニーズに応じた適切な支援を提供することが重要です。
ここからが【社会の理解】の第17問目になります!
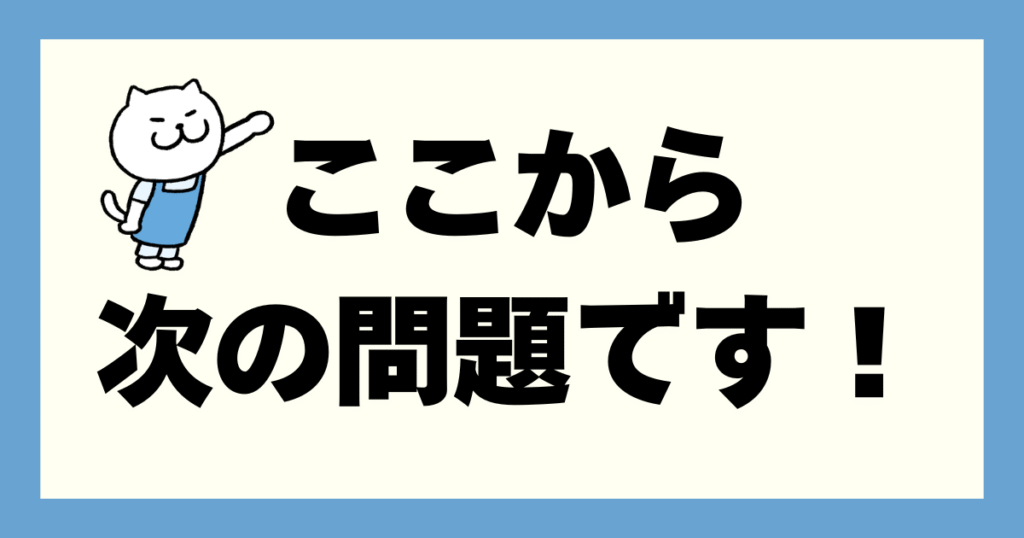
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解:1番「高齢者住まい法」に基づく,高齢者のための住まいである。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは
サービス付き高齢者向け住宅は、平成23年10月に施行された「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)の改正により創設された住宅制度です。
高齢者が安心して住み続けられる住まいの確保を目的として、バリアフリー構造等の住宅と、見守りや生活相談等のサービスを提供する住宅です。
問題17の各選択肢の解説
| 選択肢 | 内容 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「高齢者住まい法」に基づく,高齢者のための住まいである | ○ 正解 | サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)に基づいて設立された住宅制度です。 |
| 2 | 65歳以上の者が,市町村の措置によって入居する | × 不正解 | 措置入所ではありません。利用者が事業者と直接賃貸借契約を結んで入居します。また、対象は60歳以上です。 |
| 3 | 認知症高齢者を対象とした,共同生活の住居である | × 不正解 | これは認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の説明です。サ高住は認知症に限定されません。 |
| 4 | 食事サービスの提供が義務づけられている | × 不正解 | 食事サービスは義務ではありません。事業者が任意で提供するサービスです。 |
| 5 | 介護サービスの提供が義務づけられている | × 不正解 | 介護サービスは義務ではありません。必要に応じて外部の介護サービス事業者と契約します。 |
第17問目のまとめ
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、高齢者住まい法に基づいて創設された高齢者向けの住宅制度です。
重要なポイント:
- 法的根拠:高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)
- 契約形態:利用者と事業者の直接賃貸借契約(措置ではない)
- 必須サービス:安否確認サービスと生活相談サービスのみ
- 任意サービス:食事サービスや介護サービスは義務ではなく選択可能
- 対象者:60歳以上(65歳以上ではない)
- 住宅の性格:認知症専用ではなく、一般高齢者向けの住まい
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられる環境を提供することを目的とした住宅であり、介護施設とは異なる「住まい」としての性格が強いことを理解することが重要です。
ここからが【社会の理解】の第18問目になります!
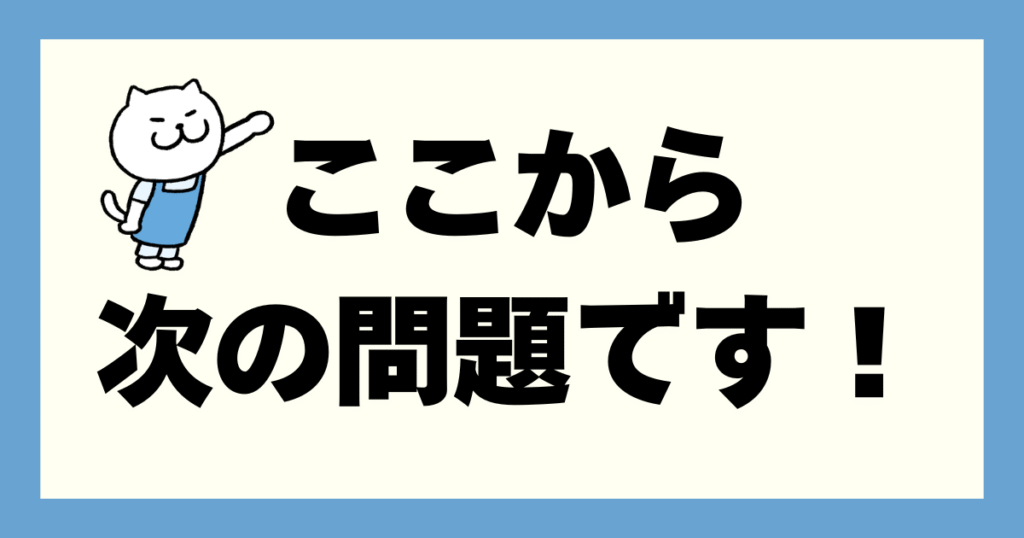
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解:4 医療保険制度
事例の分析
本事例のポイントを整理すると以下のとおりです:
- 発症場所:自宅(休日の趣味活動中)
- 発症状況:家庭菜園の作業中
- 疾患:脳出血による高次脳機能障害
- 治療内容:医療機関での治療・リハビリテーション
- 年齢:60歳(現役世代)
制度選択の根拠
医療保険制度が適用される理由:
- 脳出血は疾病であり、医療保険の給付対象
- 自宅での趣味活動中の発症のため、労災保険は適用されない
- 現在進行中の治療・リハビリテーションの医療費が対象
- 60歳のため、介護保険の被保険者ではあるが、医療費の支払いは医療保険が基本
問題18の各項目の解説
| 制度 | 適用条件 | 給付内容 | 本事例での適用 |
|---|---|---|---|
| 1. 介護保険制度 | ・65歳以上または40-64歳の特定疾病 ・要介護認定が必要 | 介護サービス費用 | △ 介護が必要になれば将来的に利用可能だが、現在の医療費支払いには適用されない |
| 2. 労災保険制度 | ・業務上または通勤途上の災害 ・労働者であること | 療養給付、休業給付等 | × 自宅での趣味活動中のため業務上災害ではない |
| 3. 雇用保険制度 | ・失業時 ・職業訓練受講時等 | 失業給付、教育訓練給付等 | × 医療費支払いとは関係がない |
| 4. 医療保険制度 | ・疾病または負傷 ・保険料納付 | 医療費の7割給付(3割自己負担) | ◎ 脳出血は疾病であり、医療費支払いの基本制度 |
| 5. 年金制度 | ・障害年金:障害等級に該当 ・老齢年金:受給年齢到達 | 年金給付 | △ 障害が残存すれば障害年金の対象となる可能性はあるが、医療費支払いとは直接関係がない |
第18問目のまとめ
正解:4 医療保険制度
Cさんの事例では、自宅での趣味活動中に発症した脳出血による高次脳機能障害の治療・リハビリテーションを受けており、これらの医療費支払いには医療保険制度が適用されます。
重要なポイント:
- 疾病による医療費は医療保険制度の基本的な給付対象
- 労災保険は業務上災害のみが対象のため、自宅での趣味活動は適用外
- 介護保険は将来的な介護サービス利用の可能性はあるが、医療費支払いの主たる制度ではない
- 雇用保険や年金制度は医療費支払いとは直接関係がない
医療保険制度により、Cさんは医療費の3割を自己負担し、7割が保険給付として支払われることになります。
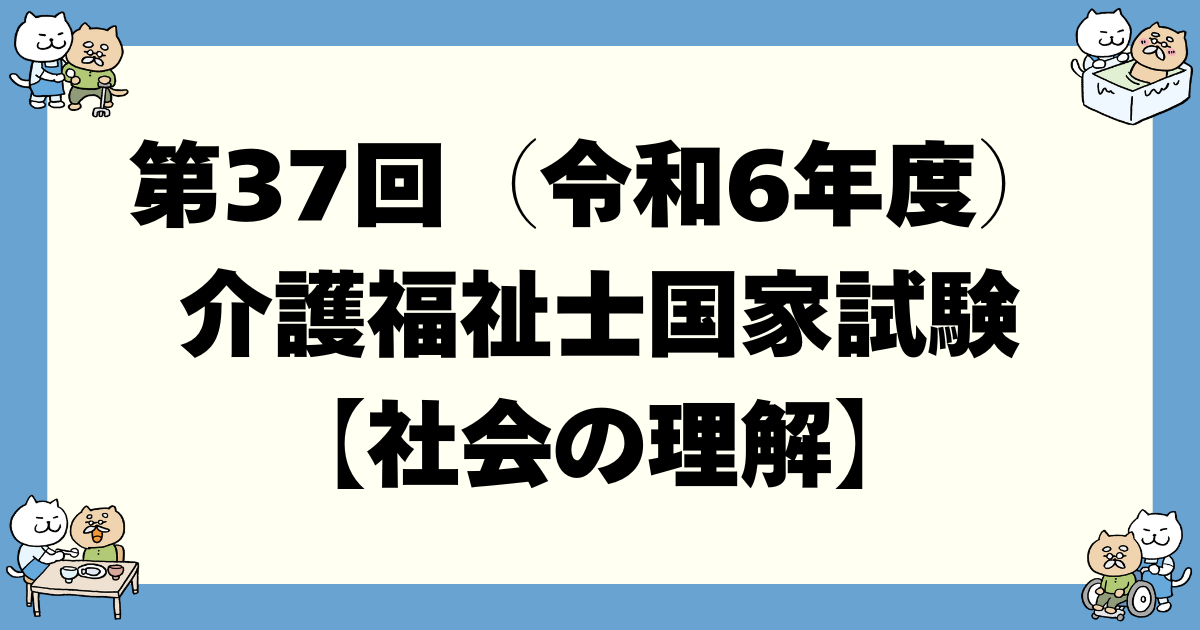
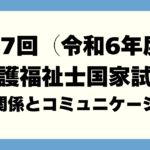
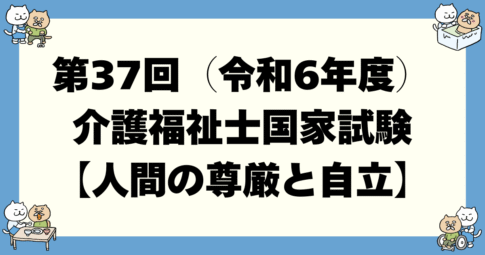
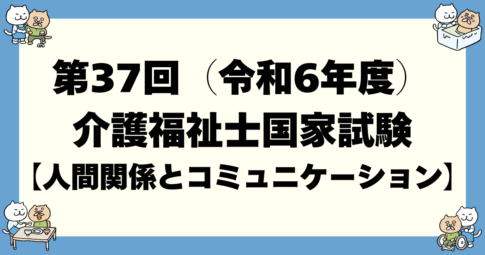
4:評議員会を置く必要がある。