こんにちは、ねこ介護士です!私は介護現場の最前線で20年以上、利用者様と向き合ってきた現役の介護福祉士なんです。
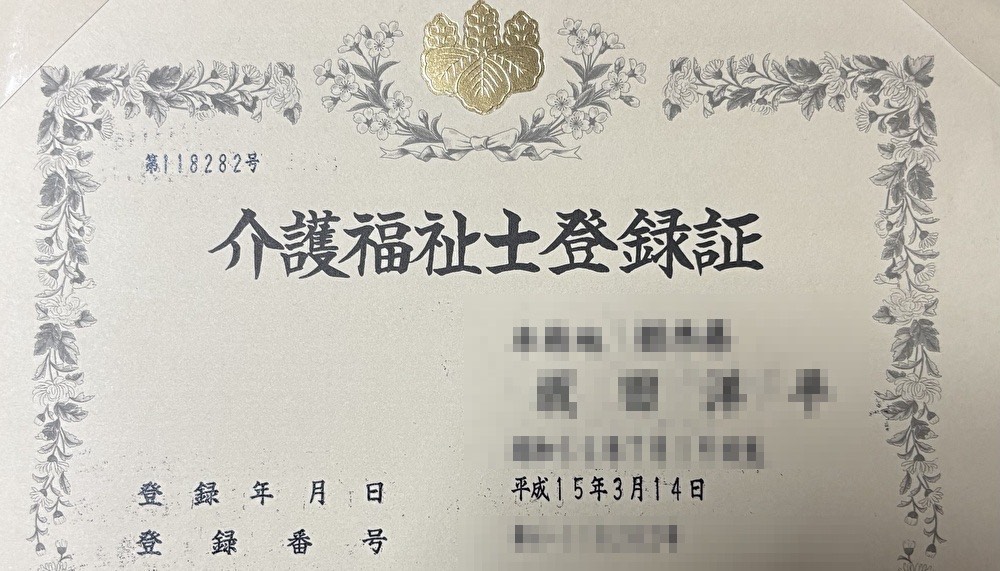
私の解説は、正解の理由はもちろん、不正解の選択肢の根拠、さらには「この知識、現場ではこう使う!」という実践的な視点まで、日本一丁寧な解説を目指して一問ずつじっくりお伝えします。
それでは、第37回(令和6年度)介護福祉士国家試験の過去問題【人間関係とコミュニケーション】の解説、スタートです!
第37回【人間関係とコミュニケーション】の過去問題
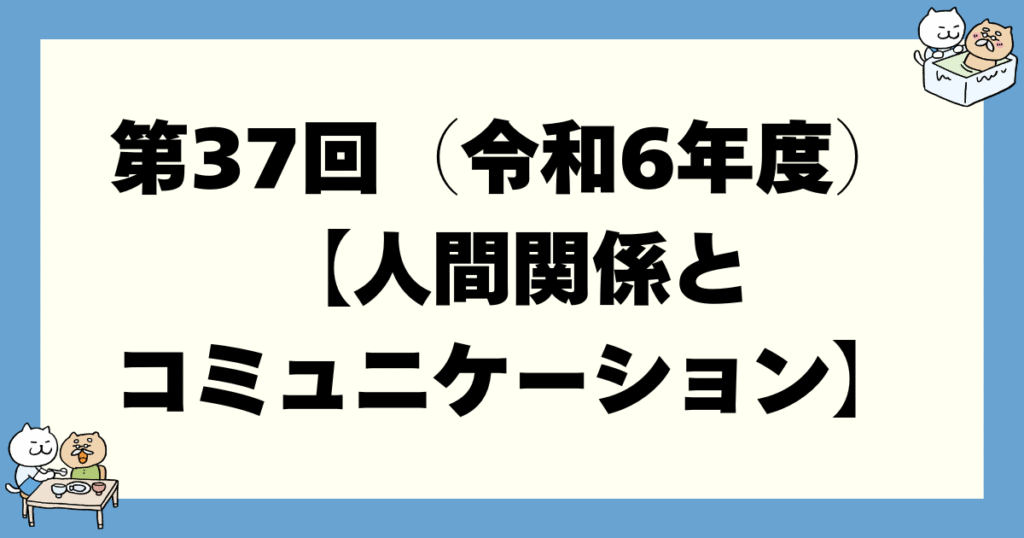
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
心理学的概念の整理
| 概念 | 正しい定義 | 特徴・補足 |
|---|---|---|
| 自己愛 | 自分自身を愛し、価値ある存在として認める感情 | 健康的な自尊心から病的なナルシシズムまで幅広い |
| 自己同一性 (アイデンティティ) | 「自分とは何か」という一貫した自己認識 | エリクソンが提唱。青年期の重要な発達課題 |
| 自我 | 現実原則に従って行動を調整する心的機能 | フロイトの理論。意識的で合理的判断を行う |
| 自己覚知 | 自分自身の感情・価値観・行動パターンを客観視すること | 援助職に必要な技術。自己理解を深める |
| 自己中心性 | 自分の視点でのみ物事を考える傾向 | ピアジェの理論。幼児期の認知特徴 |
問題3の各項目の解説
選択肢1:自己愛について
× 「自分という存在を,他人と区別して意識すること」
正しくは:これは「自己意識」や「自他の区別」の説明です。
自己愛の正しい定義:自分自身を愛し、価値ある存在として肯定的に捉える感情です。健康的な自己愛は自尊心の基礎となりますが、過度になるとナルシシスティック・パーソナリティ障害につながる可能性があります。
選択肢2:自己同一性について
○ 「自分とは何かという認識をもつこと」
正解理由:エリクソンの発達理論における「アイデンティティ(自己同一性)」の正確な定義です。
詳細説明:
- 青年期(12-18歳)の主要な発達課題
- 自分の価値観、信念、目標の統合
- 「自分らしさ」の確立
- 時間的・空間的な一貫した自己認識
選択肢3:自我について
× 「表面化していない意識のこと」
正しくは:これは「無意識」の説明です。
自我の正しい定義:フロイトの精神分析理論において、現実原則に従って合理的判断を行う心的機能です。意識的で、エス(本能)と超自我(道徳)の間を調整する役割を担います。
選択肢4:自己覚知について
× 「コミュニケーションにおいて自分について話すこと」
正しくは:これは「自己開示」の説明です。
自己覚知の正しい定義:自分自身の感情、価値観、偏見、行動パターンを客観的に認識・理解することです。特に援助職において重要な技術とされています。
選択肢5:自己中心性について
× 「自分の意思で自分の行動をコントロールすること」
正しくは:これは「自己制御」や「セルフコントロール」の説明です。
自己中心性の正しい定義:ピアジェの認知発達理論において、自分の視点からのみ物事を捉え、他者の立場や観点を理解できない思考特徴です。主に前操作期(2-7歳)の幼児に見られます。
第3問目のまとめ
この問題は心理学の基本的概念の正確な理解を問う問題でした。
特に自己同一性(アイデンティティ)は、エリクソンの心理社会的発達理論の核心的概念であり、人間関係や社会適応において重要な役割を果たします。各概念の混同を避け、正確な定義を理解することが重要です。
ここからが【人間関係とコミュニケーション】の第4問目になります!
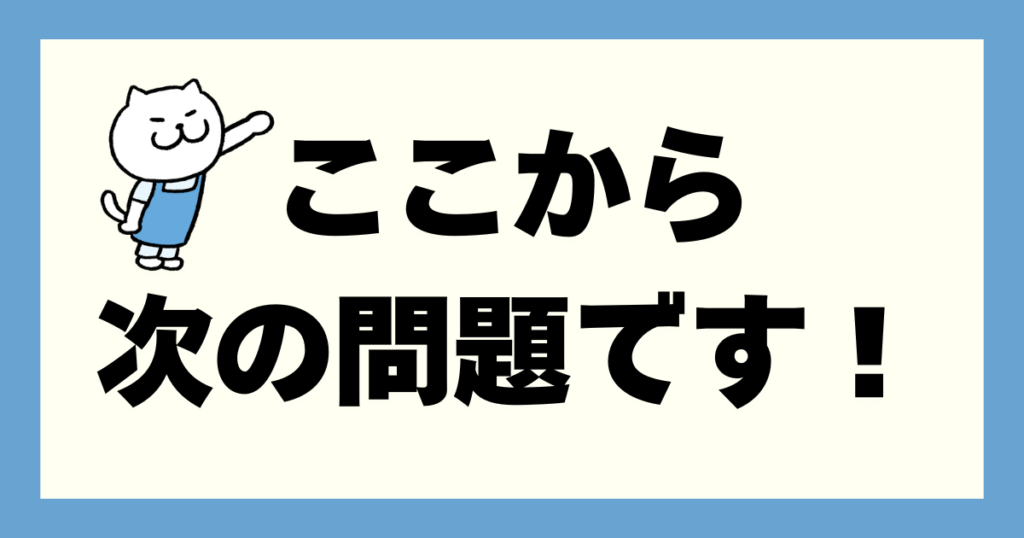
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
5番:双方向のやり取り
問題の核心
この問題は、介護福祉職が利用者との初回面接において、「一方的な働きかけにならないように」という配慮のもとで行った具体的な対応(あいづちを打ちながら発話を引き出す)の意図を問うています。
問題4の各項目の解説
| 選択肢 | 内容 | 適切性 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 1. 互いの自己開示 | お互いの個人的情報を開示し合うこと | × | 問題文では介護福祉職が自分のことを話している記述がない。一方的な働きかけを避けるための対応が焦点。 |
| 2. コミュニケーション能力の評価 | 利用者の会話能力を査定すること | × | 評価が目的ではなく、利用者との関係構築が目的。あいづちは評価のための手段ではない。 |
| 3. 感覚機能の低下への配慮 | 聴覚や視覚機能の低下に対する配慮 | × | 問題文に感覚機能の問題についての記述はない。戸惑いは心理的な要因によるもの。 |
| 4. 認知機能の改善 | 認知機能を向上させること | × | 認知機能に関する記述はない。また、あいづちが認知機能改善の手段とは考えにくい。 |
| 5. 双方向のやり取り | お互いが話し、聞き合う相互的なコミュニケーション | ◎ | 「一方的な働きかけにならないように」という記述と完全に一致。あいづちによって利用者の発話を促進し、対話を成立させようとしている。 |
第4問目のまとめ
この問題では、介護福祉職の基本的なコミュニケーション技法である「傾聴」の目的を理解することが求められています。特に「一方的な働きかけにならないように」という配慮は、利用者との双方向のやり取りを実現するための重要な姿勢です。
初回面接において、利用者が戸惑いを見せている状況では、まず相手が話しやすい環境を作り、対話を通じて信頼関係を築くことが最優先となります。あいづちはその基本的かつ効果的な手段として位置づけられます。
ここからが【人間関係とコミュニケーション】の第5問目になります!
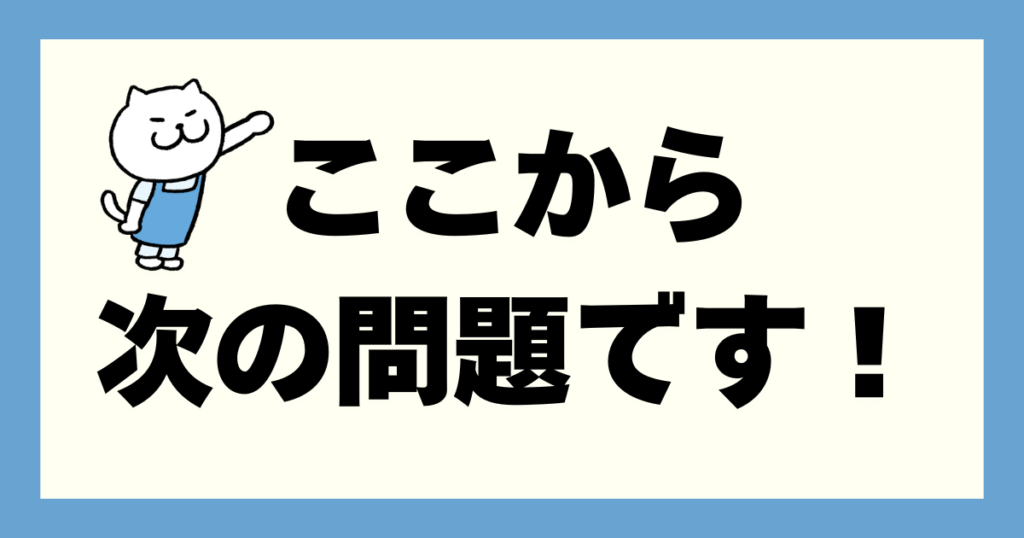
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
5番:「介護福祉職として必要な能力や経験を明確にする」
キャリアパスの定義と重要性
キャリアパスとは、職業人生において目標とする職位や職種に到達するために必要な経験、能力、資格などの道筋を体系的に示したものです。介護福祉職においては、専門職としての成長段階と各段階で求められる能力を明確化することで、職員の計画的な人材育成と職業的発展を支援する重要な仕組みです。
問題5の各項目の解説
選択肢1:介護計画を作成するときのポイントを明確にする
これは介護業務の具体的な手法に関する内容であり、キャリアパス(職業的成長の道筋)とは直接関係ありません。
選択肢2:介護福祉職の業務マニュアルを具体化する
業務マニュアルは日常業務の標準化に関するものであり、職員の長期的なキャリア発展とは異なる概念です。
選択肢3:利用サービスに応じて求められる関係書類を検討する
これは事務処理や書類管理に関する内容で、職員のキャリア発展の道筋とは関連性が低い事項です。
選択肢4:介護施設に必要な設備基準について確認する
設備基準は施設運営の法的要件に関するものであり、個人のキャリア発展とは直接的な関係はありません。
選択肢5:介護福祉職として必要な能力や経験を明確にする(正解)
これがキャリアパスの本質的な要素です。職員が目標とする職位に到達するために必要な能力、経験、資格などを段階的に明確化することで、計画的な人材育成と職業的発展が可能になります。
第5問目のまとめ
介護福祉職のキャリアパスとは、専門職としての成長段階と各段階で必要な能力・経験を体系的に示すものです。
選択肢5の「介護福祉職として必要な能力や経験を明確にする」は、まさにキャリアパスの核心的な要素であり、職員の計画的な成長と組織の人材育成戦略の基盤となる重要な取り組みです。
ここからが【人間関係とコミュニケーション】の第6問目になります!
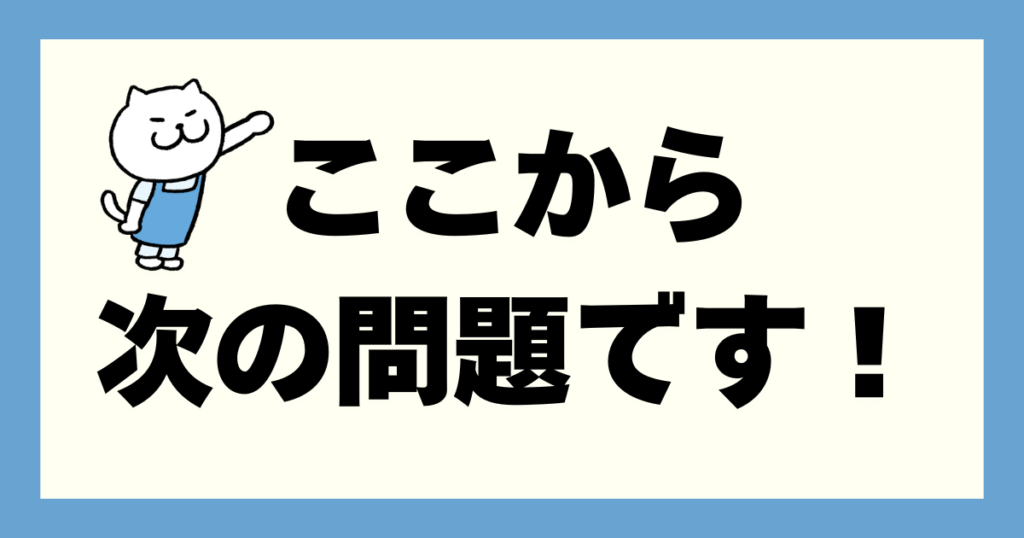
著作権保護の観点から、問題文を直接ここに載せることができません。恐れ入りますが、以下のリンクからご参照いただけますようお願いいたします。
正解と解説は以下にあります!
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
2番:ユニットリーダーが気になっていることを詳しく聞く。
フォロワーシップとは
フォロワーシップとは、組織やチームにおいて、リーダーを支援し、組織目標の達成に貢献するメンバー(フォロワー)の行動や姿勢のことです。
フォロワーシップの主な要素:
- 積極性:自ら考え、行動する姿勢
- 協調性:チーム全体の調和を重視する
- 支援性:リーダーや同僚をサポートする
- 建設的批判:必要に応じて適切な意見を述べる
- 責任感:自分の役割を理解し、責任を持つ
問題6の各項目の解説
| 選択肢 | 内容 | 分析 | 適切性 |
|---|---|---|---|
| 1 | C介護福祉職に対して,元気を出すように励ます | 状況を把握せずに励ますのは表面的な対応。根本的な問題解決にならない可能性が高い。 | 不適切 |
| 2 | ユニットリーダーが気になっていることを詳しく聞く | リーダーからの情報収集は問題解決の第一歩。具体的な状況把握により適切な支援方法を検討できる。 | 適切 |
| 3 | C介護福祉職の状況をユニット内のほかのメンバーと速やかに共有する | 詳しい情報収集前の拙速な情報共有は不適切。プライバシーの問題もある。 | 不適切 |
| 4 | 施設長に対して,何か指示を出すようにお願いする | 状況把握前に上位者に報告するのは段階を飛ばした対応。まずは現場レベルでの対処を検討すべき。 | 不適切 |
| 5 | C介護福祉職に対して,介助方法について教える | 問題の原因が技術的な面にあるかどうか不明な段階での対応。的外れな可能性がある。 | 不適切 |
さらに詳しい解説
なぜ選択肢2が正解なのか
フォロワーシップにおいて最も重要な行動の一つは、適切な情報収集と状況把握です。D介護福祉職がとるべき最初の行動は、リーダーであるユニットリーダーから詳細な情報を聞くことです。
情報収集の重要性
- 問題の具体化:「笑顔が少ない」「いつもと違う」という抽象的な情報を具体化する
- 原因の推測:仕事上の悩み、人間関係、技術的な問題など原因を特定する手がかりを得る
- 適切な支援方法の検討:具体的な情報に基づいて効果的な支援策を考える
- リーダーとの連携強化:リーダーの観察や考えを共有することでチーム連携を深める
第6問目のまとめ
この問題は、介護現場における効果的なフォロワーシップの在り方を問う重要な設問です。
チーム医療・チームケアが重視される現代の介護現場において、メンバー一人ひとりが適切にリーダーを支援し、同僚をサポートする能力は不可欠です。
特に新人職員の支援においては、表面的な励ましや一方的な指導ではなく、まず状況を正確に把握し、その人に必要な支援を見極めることが重要です。
そのための第一歩として、リーダーからの詳細な情報収集は欠かせない行動といえるでしょう。
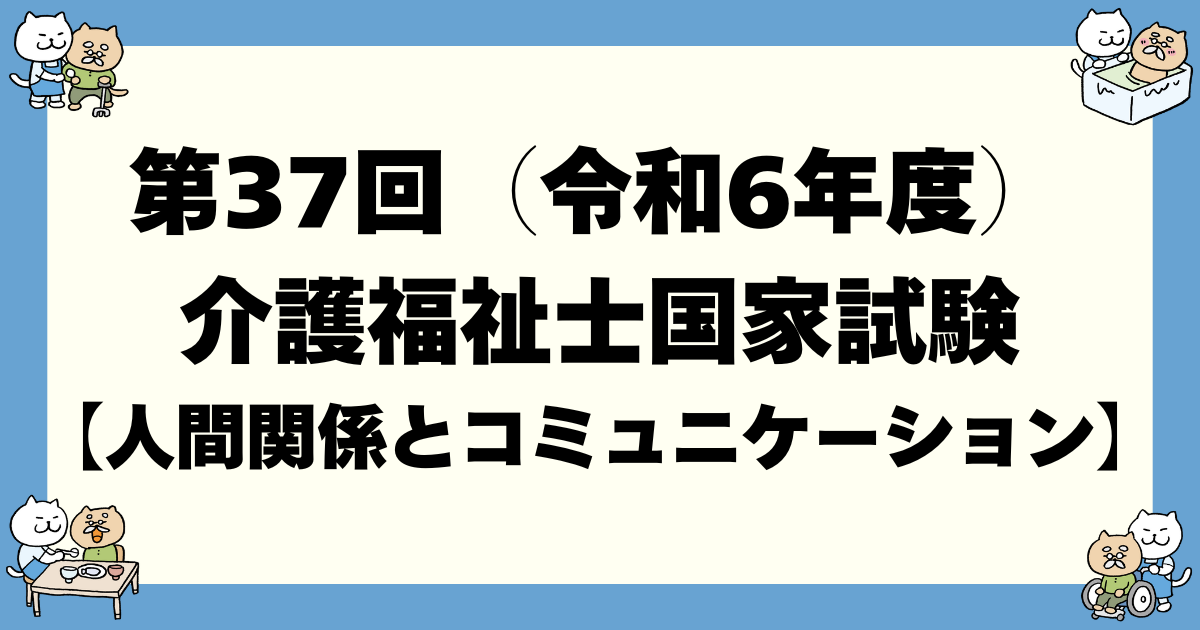
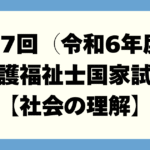
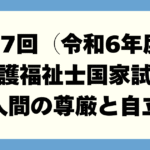
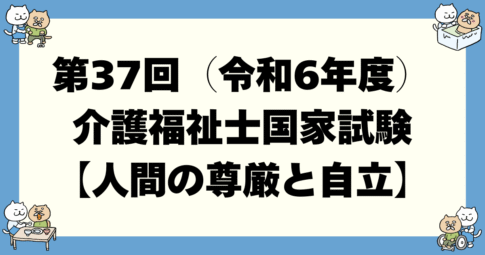
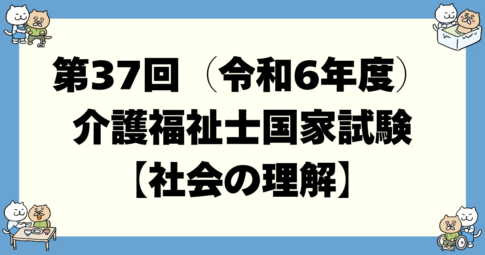
選択肢 2:自己同一性の確立とは,自分とは何かという認識をもつことである。